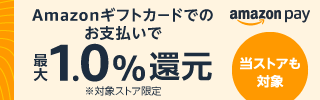8年ほど前にはじめて「茶経」を読んだ時、意外にも精神的なものへの言及が少ないということに驚いた。全編を通して、二箇所か三箇所くらいだったのではなかろうか。
布目潮渢氏の解説書を頼りに読んだのだが、陸羽が書いた内容は、基本的に当時の茶のハウツーであり、茶道具の説明書であり、図像のないカタログという印象が強い。これが後世に遺ったのは、茶について書かれた史上初の書物であるということ、また、当時の茶の作法を易経的な世界観と結びつけようとする意思があったからだと思われる。
陸羽の時代の茶はいまの中国茶の姿とは違うので、実際、自分で茶を淹れて飲んでいても陸羽の文章を思い返したり意識したりすることはない。正直、読んだ内容の細かい点は、もうほとんど忘れてしまっている。
ところが、折に触れ、湯気にけぶる茶海の滴をぼんやり見ていたり、濡れて光る葉底を指で何気なく弄んでいる時などに、ふと陸羽のことを思い出すことがある。
それは、「茶経」の中味ではなく、解説書にあった、陸羽のあるエピソードである。
御史大夫の李季卿が江南に行った時、常伯熊が茶をうまく点てるというので、李公は点ててもらうことになった。伯熊は黄被衫に烏紗帽というきちんとした服装をして、手に器を執り、茶名をぴたりと言いあて、見別けて点てたので、左右は熟視した。茶が点ち、李公は二杯も飲んだ。
また李公は、陸羽が茶をうまく点てると聞き、陸羽に茶を点ててもらうことになった。
陸羽は野人の服を着け、茶器をもって入ってきて、坐席につくと、点て方は伯熊と同じであったので、李公は陸羽を軽蔑した。茶が終わると、下僕に命じて、銭三十文で煎茶博士の報酬とした。
このころ陸羽は長江のほとりを旅行し、名流の人たちに馴れ親しんでいたが、李公からこの恥辱を受けると、「毀茶論」を著した。
布目潮渢『中国喫茶文化史』(岩波書店)より
これは、封演「封氏聞見記」の一節からの孫引きである。
ここで触れられている陸羽の「毀茶論」を読んでみたいと思い、先日調べ直したら、「毀茶論」は散逸してしまい、本文が残っていないことを知った。
いや、散逸した、ということも忘れてしまっていたのかもしれないが、いずれにせよ「毀茶論」は陸羽の同時代の書物で触れられているのみで、中味は想像するしかないようだ。
いくつかの同時代の叙述では、陸羽は富や権力を嫌った人物として描かれている。ある詩の中では、陸羽が野山を歩いて茶を探し、山中で野宿をする様子も歌われている。
また、「全唐詩」の中には、陸羽自身の作とされる有名な詩がある。
不羡黄金罍 不羡白玉杯 bú xiàn huáng jīn léi bú xiàn bái yù bēi
不羡朝入省 不羡暮登台 bú xiàn cháo rù shěng bú xiàn mù rù tái
千羡万羡西江水 曾向竟陵城下来 qiān xiàn wàn xiàn xī jiāng shuǐ céng xiàng jìng líng chéng xià lái
黄金の酒器も白玉の杯も望まない
朝廷に入り官吏になることも望まない
私がただ望むのは、竟陵城を流れる西江水のことだけだ
多分にルサンチマン的な心情を詠っているともいえるが、実際に陸羽は太子任官の誘いを断っていたりもするので、能力や人望がなかったわけではない。世捨て人というわけでもなく、むしろ、パトロン的な支援者や文人・官僚との交友によりその名を馳せたというのが実情である。
この詩を書いたきっかけも、陸羽を拾って育てた故郷・竟陵の智積禅師の訃報と伝えられている。
なので、最後の句も、単純に考えれば「故郷の竟陵に帰りたい」という意になるのだが、「西江水」を「茶」に見立てていると解すこともできるので、陸羽の茶への傾倒を表現しているとするのが一般的な解釈である。
また、「西江水」は、馬祖禅の語録(一口吸尽西江水)にもあり、陸羽がそれを知らなかったはずはないので、茶と禅との合一世界の表象と読む向きもある。
この詩や「毀茶論」のエピソードから窺われるのは、茶と政治、茶と権力、あるいは茶と富というように、茶を世俗から離れた聖なるものとして捉えようとする、陸羽の二元的な思考である。
聖と俗というテーマはありふれたもので、陸羽にかかわらず唐代の詩人・文人全般に見いだされるものかもしれないが、陸羽の場合は茶が全面的にクローズアップされるので、大変に興味深い。
これと同じテーマは、日本では、利休と秀吉の関係、もしくは、利休とその弟子の山上宗二の関係に見ることができるだろう。
1989年の映画「利休」(勅使河原宏監督、赤瀬川原平脚本)では、秀吉の金の茶室に対して、利休は曖昧な態度をとっているかのように演出されている。
利休にとって秀吉はパトロンであり、自らの茶を広めるには秀吉の財と権力は必要不可欠なものであるという如才ない判断がある。
このシーンで秀吉と正面から対立するのは、利休ではなく、利休の弟子の宗二である。
後半の利休と宗二の会話は、芸術論としても心理ドラマとしても、非常に面白いものになっている。
宗二「度々お心を煩わせて申し訳ございません。私は節を曲げない質ですので」
利休「それではいかにも、この、わしが・・」
宗二「宗匠様は何を仰っても通るお方ですから。・・・良い機会です。出ていきます」
利休「どこへ」
宗二「茶湯者は純粋に茶湯者であるべきで、それを生活のたづきになさるのを、嘆かわしく思っておりました。悲しいことに、私も同じ生き方をする他ないのですが」
利休「黒は、古きこころ・・」
宗二「殿下は金がお好きなのです」
利休「しかしな、宗二。金の茶室には不思議な美しさがある。あの中にいると、すうっと広がって、おおらかで、そう、無辺なのだ」
宗二「それはご自分がお造りになったからでしょう」
利休「お前は逆に、金の値打ちに毒されているのではないのか」
宗二「殿下に媚びていらっしゃるんだと思います。侘びの草庵とはまったく違う。宗匠様の襞の多いお考えは、わたしは呑みこめません」
利休「わしにはふたつを分けて考えられんのだ」
宗二「矛盾しております」
このような会話が、おそらくは「毀茶論」を著わしている陸羽の中で、自己問答としてなされていたのではないか。
体系の創始者は、同時に、その体系の破壊者であることが多い。
ひとたび体系が完成してしまえば、それは、体系にとっての死と同義だからである。それ故、創始者の言動は、常に矛盾を内包したものにならざるを得ない。
陸羽も利休も、ともに厄介な存在である。
小林
小林
過去のブログ記事
最近のブログ記事
丽日茶記リーリーチャージーより